社会人口学を専門とする国際教養学部の皆川友香准教授は、社会環境が個人に及ぼす影響について研究しています。平均余命だけでなく、幸福度や満足度を加味した「健康余命」の視点から人々の健康状態を明らかにしたいと語ります。
私の専門は、社会・経済的な要因から国・地域の人口変化を研究する社会人口学です。旧ソ連地域や日本を対象に、個人を取り巻く社会環境が身体的、精神的な健康状態に与える影響について定量的に分析してきました。
大学卒業後に進学したハーバード大の大学院で出合ったのが社会学です。当時、旧ソ連地域に関する研究は政治経済の分野が中心で、社会学からのアプローチは手つかずといってもいい状態でした。その後、人口学の分野でアメリカ有数のテキサス大学オースティン校で学び、社会人口学的な観点から旧ソ連地域の健康状態を研究する道に入りました。
1996年、オランダの社会学者フェーンホーヴェンが、疾病の有無を指標としたマイナスの健康状態ではなく、幸福度や満足度といったプラスの健康状態に注目することの重要性を示しました。国民の健康状態は平均余命で測られることが多い。ただ、生活習慣病の増加や医療の高度化に伴い、人は病気になっても治療を受けながら生きられるようになりました。平均余命だけでは人々の健康状態を図れない時代になったのです。
幸福度や満足度を加えて健康状態を測る

平均余命のうち、健康に暮らせる期間を健康余命といいます。人生の長さだけでなく、幸福度や満足度といった包括的な視点から健康状態を捉えようとする考え方が健康余命の根底にあります。私は日本大学の研究者と共同で、ロシアとカザフスタン、キルギス、タジキスタンの中央アジア3カ国の健康余命を調査し、その研究成果は2023年、国際学術誌にオンライン掲載されました。
この研究で明らかになったことは、中央アジア3カ国はロシアよりも経済発展レベルが低いにもかかわらず、国民はロシアよりも健康で、幸福な生活を享受しているということです。生活習慣、宗教、社会的・文化的特徴など、さまざまな要因があると考えられますが、健康の定義に関する重要な示唆を与えるものだと考えています。
健康に関する研究は、病気を治すための治療法や新薬の開発といった医学的な側面に力点が置かれがちです。ただ、人が病気になるプロセスを明らかにすることも重要です。家庭や職場といった個人を取り巻く社会的環境からアプローチする社会人口学の果たす役割はとても大きいのです。
女性の健康状態が悪化している要因を明らかにしたい
2023年9月、中山人間科学振興財団の「健康格差のヒューマンサイエンス」をテーマとした応募研究で、私の「男性・女性の健康格差に関する社会学的考察」が中山賞奨励賞を受賞しました。他の受賞者が全員医学者のなか、社会学者の受賞は私一人でした。国民皆保険制度のある日本において、健康格差は顕在化しにくいのですが、社会学的な観点からそれを明らかにしようとする私の研究業績が評価されたのだと考えています。
男性より女性の平均余命が長いことは日本だけでなく、世界的な傾向です。ただ、健康状態については男性より女性のほうが悪くなっているといわれます。ジェンダー・パラドックスと呼ばれるものです。ジェンダー格差が社会のあらゆる面で指摘される日本において、女性が担っている子育てなどの観点から、女性の健康状態が悪化している要因について、今後明らかにしたいと考えています。
この一冊
『カラマーゾフの兄弟』
(フョードル・ドストエフスキー/著)
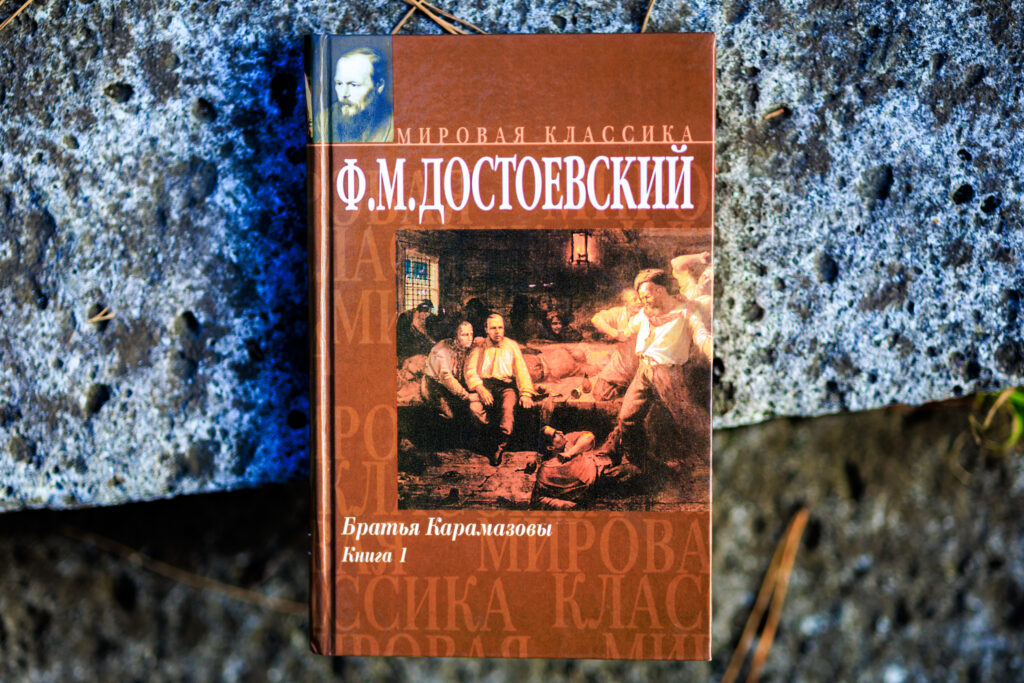
学生時代に病気を患い、「なぜ自分だけがこんな目に遭うのか」との葛藤がありました。そのなかで「人生を恐れてはいけない」というアレクセイ・カラマーゾフの言葉が私の精神的な救いになったのです。
-
皆川 友香
- 国際教養学部国際教養学科
准教授
- 国際教養学部国際教養学科
-
上智大学外国語学部ロシア語学科卒。ハーバード大学ロシア・東欧・中央アジア地域研究修士課程修了。テキサス大学オースティン校にて博士号取得(社会学)。早稲田大学高等研究所助教を経て、2017年より現職。
- 国際教養学科
※この記事の内容は、2024年1月時点のものです
