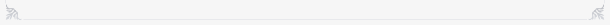第13回 輝くソフィアンインタビュー 二宮くみ子さん
第13回 輝くソフィアンインタビュー 二宮くみ子さん
![]()
第13回 輝くソフィアンインタビュー 二宮くみ子さん
2013.03.18
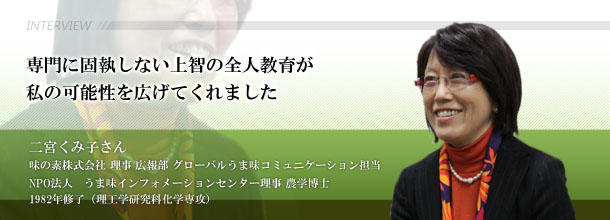
二宮 くみ子さん
味の素株式会社 理事 広報部 グローバルうま味コミュニケーション担当
NPO法人 うま味インフォメーションセンター理事 農学博士
1982年修了(理工学研究科化学専攻)

世界を飛び回っています
みなさんは「うま味」と聞いて、どんな味を思い浮かべますか? 昆布やカツオでとったダシの味といえばピンとくる方が多いと思います。しかしながら、「うま味」を発見したのが池田菊苗という日本人学者だったこともあり、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」と並び、味を構成する基本味であるにも関わらず、世界ではあまり認知されていなかったのです。そうした背景もあり、私は味の素株式会社に入社した1982年から今に至るまで、国内外で「うま味」の普及活動を行ってきました。
入社後にまず取り組んだのは、世界の研究者や大学教授の研究サポート、「うま味」に関する国際シンポジウムのアレンジなどを通じた普及活動です。欧米には「ダシ」の文化がないので、例えば「うま味物質のグルタミン酸やイノシン酸の存在を自分で裏付けているのにも関わらず、どんな味なのか試したことがない」という研究者がいたりします。そうしたところをフォローして、世界の研究者のみなさんに化学や食品、脳科学など、いろんな方面からうま味について発表していただきました。
研究者向けの活動を行った後、広報部へ異動になり、現在は一般向けの普及活動を担当しています。食育の一環として味覚教室を開催し「うま味」を体験してもらうなど、現在もさまざまな取り組みを実施中。欧米をはじめ、南米やアフリカなど世界各地に赴き、現地の方々に「うま味」を紹介することも。ちなみに、海外では日本と同じように昆布やカツオを用いて説明してもダメ。欧米の場合はトマトやチーズ、野菜のブイヨンを用いるなど、馴染みのある食材で「UMAMI」を体験させたほうが納得してもらえます。今後もこうした活動を続けて、世界に「うま味」の正しい知識を広めたいですね。

原点に返り、深く理解することの大切さ
学生時代の私は、筋金入りの理系女子でした。高校時代は化学や物理が得意科目でしたし、故松本重一郎先生の研究室で学ぶために上智大学の理工学部しか受験しなかったくらいです。
松本先生に学んだことは数多くありますが、今も忘れないのは「原点に返る」ことの大切さ。人づての知識で満足することなく、必ず自分の目でオリジナルの論文を読み、理解すべきという考えです。もし、それが英語の論文なら、自分で翻訳しながら読むので、それなりの時間がかかります。でも、その分、多くの気づきを得られますし、「理解するために自分はここまでやった」という自信にもつながるわけです。
院生時代に行った研究も忘れられません。「人がやっていないことをやろう」と意気込んでテーマを探したのはいいけれどなかなか見つからず、悩んだ末、魚の筋肉組織を比較するというテーマで研究を始めました。当たり前ですが、誰もやっていないことに取り組んだので、教えてくれる人はいません。研究に使う電子顕微鏡を使いこなすまでに半年もかかるなど、かなり悪戦苦闘しました。実験の素材となる魚を集めるために、松本先生や研究室の仲間を誘って海釣りに出かけたこともありましたね。その甲斐あって、いろんな魚の筋肉組織を写真として残すことができました。今ではもっとよい撮影機器が出ていますが、当時としては貴重な資料を作ることができたと自負しています。

(The Consumer Goods Forum主催)でのうま味セッション。
日本も多様なローカルのひとつととらえること
今でこそ一年の3分の1を海外出張で過ごしていますが、学生時代、英語は苦手科目。「こんな英語のできない学生は初めてだ」と言われたことも。英語は仕事の必要に迫られて自分で学びましたが、語学の習得には「コミュニケーションしたい」「伝えたい」という気持ちが一番大切だと思います。味の素は入社当時から海外に展開していたいわゆる「グローバル企業」です。グローバルという言葉は、つい「日本と海外」という対比で捉えがちですが、日本もたくさんあるローカルのうちのひとつだ、という視点を持たないと、本当の意味でのグローバルな視点はできてこないと思います。他学部の学生や外国人の先生方、多様な人々と触れ合えた上智での学びは私の原点です。若いみなさんにも上智で学んだ誇りをもって自分を活かせる場所を見つけてほしいと思います。

交えて、うま味について語る。
可能性を広げるためのもの
私は学びを深めるために大学院まで行きましたし、自分の経歴や研究実績から最初は会社では「理系出身の堅い女が入ってきた」と思われていたようです。事実、研究職志望で入社したので、望みがかなわないことに不満を感じていた時期もありました。でも、今ではむしろ、生物化学を学んだわずか4~5年の経験に縛られて、自分を制限しなくてよかったと考えています。もちろん、大学の学びは大切にすべきですが、何十年という長い人生の中で見れば、あくまで基礎にしかなりません。それにも関わらず、「自分はこれが専門です」と決めつけてチャンスの芽を摘んでしまうのはもったいないこと。大学での学びを活かしつつ、もっと大きな可能性を探るべきだと思うのです。このあたりの考え方は、ガラルダ先生の人間学の授業で、ヒューマニズムや人と人との関わりについて学んだ経験が生きているのもしれません。
もう一つ、昔の私と同じように自分の希望がかなわず、会社に働かされていると感じている方に伝えたいことがあります。これは「うま味」の普及活動を通じて実感したことですが、「自分一人が世の中に対してできることは小さいけれど、会社を通じてならば大きな影響を与えられる」ということ。とくに若い方は、「○○しかやりたくない」なんて思わずに、何でもやってみたほうがいいのではないでしょうか。自分が会社を通じて社会にどのような貢献をしているのか考えられるようになれば、きっと今よりも仕事を楽しめるはずです。
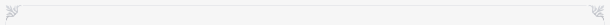
1980年 上智大学理工学部化学科卒業
1982年 上智大学理工学研究科化学専攻修了
1982年 味の素株式会社入社
1985年 NPO法人うま味インフォメーションセンターに参画
約30年もの間、味の素の広報部グローバルうま味コミュニケーション担当、うま味インフォメーションセンターなどの活動を通じて、「うま味」の啓発、普及を続けている。NPO法人うま味インフォメーションセンター理事、上智大学女性研究者支援プロジェクト外部評価委員(2010-11年度)。在勤中に広島大学大学院生物生産学部博士課程修了。農学博士。